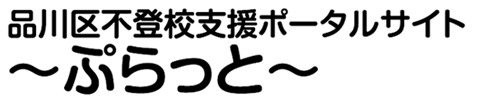更新日 2025年03月31日
学校を長い間休んでいたり、休みがちだったりする子どもたちはどう過ごしていたり、どんな気持ちを抱いているのか、調べたアンケートがあります。
文部科学省は、2019年に不登校だったけれど、2020年には、教育センターに通ったり、学校に通ったりしている中学校2年生と小学校6年生にアンケート(1)の回答をお願いしています。
アンケ―トの結果ですが、2019年に不登校だった小学生のうち、次の年には約3割はほぼ毎日、学校に通っていました。中学生では少し減ってしまうのですが、4人に1人程度が毎日のように学校に通っているようです。一度学校をお休みしてしまっても、毎日学校に通えるようになる人の割合はそれなりに高く、毎日でなくても、週に1回程度学校に通っている人も多くいます。
反対に、1年後にもまだ全く通えないという人もいて、それぞれの歩み方があることがわかります。

最初に学校に行きづらい、休みたいと感じ始めてから実際に休み始める(休みがちになる)まで、小学生、中学生ともに半数くらいの人は、保健室や相談室など、学校内にあるクラスの教室以外の別室に通ったことがあると答えていました。小学校では保健室に通っていた人の割合が約6割と高いですが、中学校では保健室や相談室、別室登校専用の教室など様々な別室に通っていた人がいました。
休んでいる間の過ごし方は、小学校、中学校共に約4割が友だちと一緒に遊んでいたり、外出したりしています。
休んでいたときの気持ちとして、小学生では6割、中学生では7割の人が「勉強の遅れに対する不安があった」と答えています。「同級生などがどう思っているかが不安だった」という人も小学生では約6割、中学生では約7割いました。
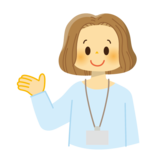
中学卒業後の進路も気になるところかと思います。
不登校だった人の中学卒業後の進路ですが、東京都ですと、全日制の高等学校のほかに、定時制の高等学校(チャレンジスクール)や通信制の高等学校(通信制サポート校含む)に進学する人もいます。それぞれの生徒の個性や経験などにあわせた多様な学びが出来るように、さまざまな配慮をした学校や特色あるカリキュラムが組まれた学校があり、自分に合った進路先を選択することで、高校進学後、生活に満足している生徒は多いようです。
自分にはどのような進路が向いているのか、家族や相談できる大人などとも一緒に考えてもらい、自分に向いていると思われる進路先を選択することが大切です。
学校のホームページを見ると、どのような特色があるか、どんなことが学べるかがわかります。学校見学会があれば、参加してみると、校舎や先生、生徒の姿から雰囲気を感じられます。
詳しい進路については「進路が心配だけど…」のページを見てください。
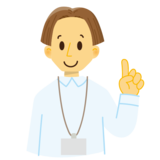
(1)文部科学省『不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書』令和3年