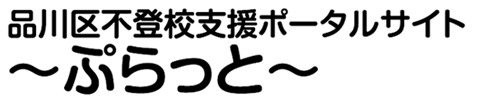更新日 2025年03月31日
不登校と関係しやすい心と体の症状
不登校時、とくに初期には、心のSOSが腹痛や頭痛などの身体症状として現れることがあります。学校を休むと症状がおさまることがありますが、心と体は密接にかかわっています。大人がストレスで胃痛になったり、高血圧になったりするのと同じです。
身体症状がある場合は、まずは医師の診察を受け、体の異常がないかを確認しましょう。
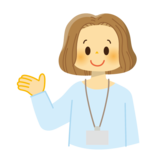
生活リズムの乱れに気をつける
「朝起きられない」は不登校の子どもに多い現象です。朝、カーテンや窓を開けて直射日光を浴びると、体内時計の調整に有効といわれます。
ただし不登校の初期など、心のエネルギーが低い時期は、ゆっくり休ませてあげることが必要なこともあります。また起立性調節障害など心や体の健康が損なわれている場合もあるため、医師と相談することも大切です。

スマートフォンなどでの動画の視聴やゲームなどが長時間続いていたり、夜更かしなどの影響が出ていたりすると、保護者としては気になるところですが、スマートフォンなどを取り上げたり、禁止したりするのは逆効果といわれます。子どもと話し合ってルールを決めることや、ゲームやスマートフォン依存についての知識を保護者が得ておくことも大切です。相談機関やスクールカウンセラーとまず相談してみてください。
「起立性調節障害」について

起立性調節障害は自律神経系の機能低下や調節不良が原因で起こる体の病気です。「朝、起きられない」「午前中は頭痛や腹痛、倦怠感が強い」などが主な症状です。小学校高学年から高校生くらいまでに現れやすく、小学生で約5%、中学生で約10%が起立性調節障害といわれています。診断には様々な検査が必要です。治療の基本は生活リズムを整える、適度な運動を行うなどの生活習慣改善と服薬です。
中学生までの起立性調節障害の診療科は小児科になります。日本小児科学会や日本小児心身医学会に所属されている医師だと安心です。
日本小児心身医学会のホームページでは、「一般の皆様へ」で、起立性調節障害などの病気の説明や起立性調節障害についてわかりやすく説明したパンフレットを紹介しています。
医師の診察を受け、起立性調節障害の診断がついたら、学校に報告し、理解と支援を求めることも大切です。