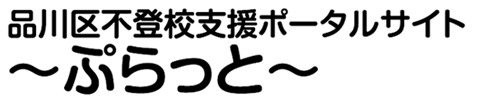更新日 2026年02月25日
心構えについて

子どもは学校に行けない自分に罪悪感などを抱いている場合がほとんどです。このようなときに、焦って学校に行かないことを責めると、逆効果になることも少なくありません。子どもが安心して次のステップに進めるよう、スクールカウンセラーなどに相談しながら保護者自身が焦らないことが大切です。
学校に行かなくなった理由を問い詰めたり、「原因を取り除けば学校に行けるはず」と原因探しをしたりしがちです。しかし、子ども自身も混乱していたり、何が起きているのかわからずにいたりする場合が多いため、弱っている子どもを追い詰めるだけです。原因探しはよい結果を生まないことが多いことを知っておくことが大切です。
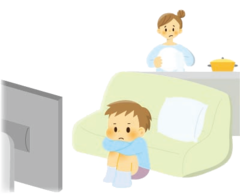
不登校は、その子の健康や成長のために必要な行動である場合も少なくありません。場合によっては、殻に閉じこもることが回復のために必要なこともあり、その時期をこえてから、外に出られる工夫が大事になる場合もあります。
その子の状態や時期によって、まったく違った対応が求められることもあります。保護者がよかれと思って反対の対応をしてしまうと、本人の成長を妨げてしまうことがあり、残念です。どういう対応が必要かの判断は、保護者だけでは難しいことも多いため、専門家に相談して、知識を得て、専門家と一緒に考えることが大切です。子どもに合った対応をすることが、早期の解決や回復、子どもの成長につながります。
保護者が子どもにできること
口出ししたくなっても、こらえて、子どもを受け入れ、見守りましょう。
学校の話題は避け、保護者の不安をそのまま口に出してしまうことは控えましょう。
お子さんが相談したい気持ちがある場合は、スクールカウンセラーなどに相談することを勧めてみましょう。自宅での学習に意欲があったり、もしくはスマートフォンなどで動画をよく見たりしているようでしたら、学びの場につながるようなサイトを紹介するなど、相談できる場所や学びの場につながる手助けをしてみましょう。
本人は焦りや不安があっても、なかなか動けないものです。そのため保護者からの提案も、強要されたように感じてしまうことも多いもの。あくまで情報提供として伝えることが大切です。
保護者自身がスクールカウンセラーなどに相談をして、子どもとの接し方や不安などを受け止めてもらったり、進級や進学先、学校以外の学びの場や子どもの居場所の情報などを集めることも役立つことが多くあります。ぜひスクールカウンセラーや相談機関などを活用してください。
返事はなくても声をかけることで、子どもはつながりを感じます。
保護者が今までと同じ日常生活を送ることは子どもの安定にもつながります。
保護者自身が精神的に安定することで、子どもに対して余裕を持った対応ができます。
相談できるところや学校以外の子どもの学びの場や居場所、Webの学びの場については、「子どもを支える専門家・相談機関など」で紹介しています。
また、中学卒業後にどのような選択肢があるかについては、「中学卒業後の進路選択について」をご参照ください。

品川区内の相談先などの情報、また、フリースクールや家庭での自主学習が指導要録上の出席扱いになるか(出席扱い要件)などをまとめたガイドブックがあります。